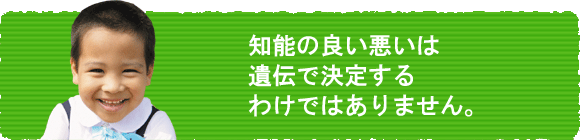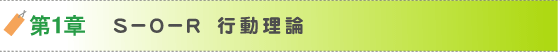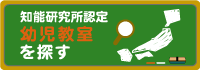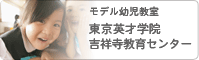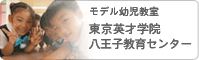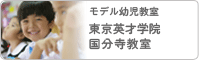アメリカの心理学者ワトソン(1878〜1958エール大学)は人間の行動は客観的観察可能な行動だけを研究の対象としました。そして人間の行動を「S(刺激 stimulus)-R(反応 response)」の簡単な図式に置き換え、全ての行動を説明しようとしました(行動主義)。
のちにこの考え方を是正する形でトールマン(1886〜1958)やハル(1884〜1952)は「S-R」の間に「O(有機的組織体・生体 organism)」を入れることにより、生体の個々の行動をより合理的に説明しようとしました(新行動主義)。
しかし当時「O(organism)」は、「Black Box」といわれ、その中身はわからないと言われました。
この「O」の中に本性論と知能因子論を導入して人間行動を説明しようとしたのが知能研究所創立者の肥田正次郎です。
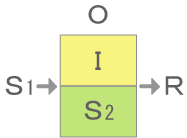
肥田は「O」の部分を2つ(知能と本性)に分けて、右のような図式で人間行動を説明しています。
この場合の「I」はintelligenceの「I」つまり「知能」を意味しています。
また「S」を「S1」と「S2」に分けたのは、[S1」が外部刺激であるのに対して「S2」を内部刺激であるとしたためです。
「S2」とは有機的組織体「O」に含まれる「本性」のことであり、本性は一般にいわれる「本能」と同義であると考えていいでしょう。
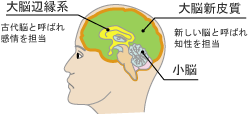
知能とは「憶える」「考える力」である。そしてそのほとんどは大脳皮質の働きであると考えます。
右図の緑の部分が大脳皮質で、新皮質とよびます。それ以外の大脳辺縁系と脳幹を合わせて旧皮質とよびます。
知能とはこの新皮質(大脳皮質)の部分の働きなのです。

〜人間は早産
人間は生まれたときは他の動物に比べて非常に未熟です。
馬や牛は、生まれて30分位で歩きます。ヒヨコも地面をつついたりします。
このように多くの動物はほとんどの行動様式が完成されて生まれてくるのです。親と同じ行動ができる。つまり成熟して生まれてくる。ということは、生後、変化する部分が非常に少ないということです。

それに比べて人間の子は、1年ぐらいしてやっと歩き出します。また生まれたときは手足をバタつかせる程度で、ほとんど何もできません。何もできないということは大脳皮質が他の動物に比べて非常に未発達な状態であるということです。 人間が未発達であるということは、逆にいえば、生後の環境で大きく変化(成長)する可能性があるといえるのです。
〜生まれたときは白紙
大脳皮質が未発達であるということは、言い方を変えれば人間は生まれたときは「白紙」であるということです。この白紙にどのような絵を描き、どのように色づけしていくかが、生後の環境であり、教育ということになるのです。
知能を分析すると、覚えたり、考えたりする「知能活動」と、何を材料として覚えたり、考えたりするのかという「「知能領域」の2つに分けることができます。
覚えたり、考えたりする材料は大きく次の3つに分けることができます。
| 図形 | かたちを組み合わせて考えたり、覚えたりする |
| 記号 | 数・色・音を組み合わせて考えたり、覚えたりする |
| 概念 | 言葉の意味で考えたり、覚えたりする |
活動は憶えることつまり「記憶」と、考えることつまり「思考」の2つに分けることができます。
記憶 次の3つの因子に分けられます
| 記銘 | その場ですぐ憶えること |
| 保持 | いつまでも覚えていること |
| 再生 | 思い出すこと |
思考 次の5つの因子にわけられます
| 受容的思考力 | 外界の情報を正しく受け止める能力。 例えば 認知能力・理解力 等 |
| 集中的思考力 | 2つ以上の事柄から1つの結論を導き出す能力。 例えば 論理的思考力・推理力 等 |
| 拡散的思考力 | 1つの事柄から色々な方面に思いをめぐらす能力。 例えば 思考の柔軟性・連想力 等 |
| 転換的思考力 | ある事柄を別の面から見直す能力。 例えば 創造性に直結する能力 等 |
| 表現力思考力 | 考えたことを外部に的確に表現する能力。 例えば 話がおもしろい・話がわかりやすい 等 |
以上のことをまとめると下のような表になります。すなわち1〜24までのひとつひとつが知能因子となります。
例えば「1」は「図形を記銘する能力」のことです。つまり、ある形をその場で直ぐに憶える能力のことをいいます。

本性(S2)とは、人間が動物として生存するために先天的にもっている必要不可欠な能力です。つまるところ=先天的能力に欠けている生物は、すでに生存できないのです。
人間もまた、赤ん坊から老人まで、すべてこの本性によるエネルギーによって動かされているのです。
故に本性は人間行動の原点であるといえます。本性は大きく5つに分けられます。
恒常性とは、生物がその個体を常に一定の状態に保っておこうとする性質で、個体を維持するために欠かせない能力です。
恒常性が破壊されると、その個体は死に至ります。
体温は人間の場合、36〜37度がいわゆる平熱ですが、何らかの刺激、たとえば風邪ウイルスなどによって急激に体温が上がると、恒常性の働きによってこの体温を下げ、元の状態に戻ろうとします。ほかに、睡眠・排泄・苦痛からの回避など恒常性による行動はすべて、自らの個体を一定の状態に維持しようという方向に働くわけです。
対敵性は、生命をおびやかす外界の敵から自らの身を守ろうとする本性です。
対敵性の要素として「攻撃性」と「逃避性」があげらます。つまり「敵に向かっていく能力」と「危険を感じて逃げる能力」のことです。人間も生物である以上、先天的に対敵性を備えています。野生の動物とちがって、人間の場合、敵におそわれるというケースは少ないですが、日常生活の中でも、対敵性という内的エネルギーによって動かされる行動は少なくありません。
子どもの世界でも、当然ながら対敵性を源とする行動は常にみられます。喧嘩をするのはもちろん対敵性によるものですが、たとえ喧嘩をしない子であっても対敵性がないということはありえません。
適応性も本性のひとつです。適応性はその要素としての「模倣反射」と「探究反射」に分けて考えることが多いです。
「模倣反射」はそのエネルギーによって「マネしたい」という欲求になり、「探究反射」は「知りたい」という探究欲になって、そのような行動をとらせることいになるのです。人間の子どもは生まれつき適応性という本性を備えていて、周りにいる人間の行動を模倣します。這っていた乳児がやがて二本足で立ち上がろうとすることさえ、「マネをしたい」という模倣性からくるエネルギーのなせるワザなのです。そのため乳児の近くに、たって歩いているモデルがいなければ、模倣する対象がないため乳児もまた立ち上がることはありません。
何かを「知ろうとする」探究反射も、あらゆる動物が先天的に備えています。興味・好奇心が強いほど社会の現象を見・模倣し・知ろうとしますから、より社会に適応しやすくなりますが、この源にあるのはやはり適応性という本性であり、エネルギーの高さといえるでしょう。
人間は生きています。しかも必ず集団をつくって生きています。
もっとも小さな集団は夫婦であり親子であり、そして家族です。そこから学校や社会・コミュニティー社会・民族社会・国家へと集団が拡大するにつれて、そこには様々な文化やシステムが介在します。
文化やシステムは明らかに知能の所産ですが、集団あるいは種属を維持する人間の原点には「性」と「集団性」という2つの本性が存在しています。
従って先の3つの本性「恒常性」「対敵性」「適応性」を「個体維持の本性」というのに対し、「性」「集団性」の2つを「種属維持の本性」と呼んでいます。性本性のエネルギーが突き上げることによって起こる性的欲求がなければ種属を維持していけないのは自明の理です。
同じ種属維持本性でも集団性の発露は性本性に比べると非常に早いです。おなかが空いた乳児が泣くのは「恒常性」によるものですが、ひと恋しさ、寂しさを感じて泣くのは「集団性」とういエネルギーに刺激されて起こる行動であると考えてよいでしょう。「集団性」はつまるところ、常に人と一緒にいたいという欲求になる本性です。一般に言う「母性」とか「帰巣本能」と呼ばれるものも、当然この集団性に含まれます。
集団性はある種属を維持するための本性なので、その要素として「リーダー性」と「フォロア性」、また「利己性」と「利他性」などが考えられます。